この一年間いろいろな本を読み進めてきました。読んでいるだけでなく、もうそろそろ提言を書き始めないといけないのですが、その前にこの2冊だけは読み終えておきたいと思います。なお、提言のアウトラインはかなり詳細に固まっているので、書き始めたら意外と早くまとめられるような気がしています。
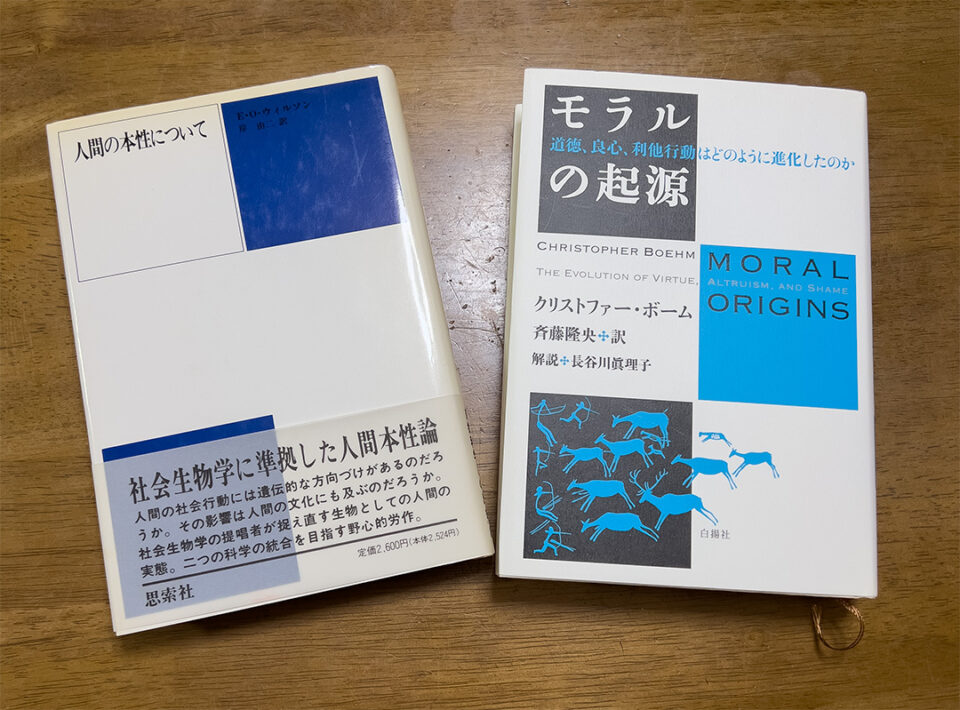
クリストファー・ボームの『モラルの起源』については、(この記事)の続編になります。紀伊國屋書店でたまたま見つけて、中古をAmazonに注文していました。本書から読み取りたい内容は、主に下記のような点です。
- ヒトの利他性の進化には、他の動物の利他行動とは異なるヒト固有の要因が関与しているらしい点
- 利他行動の進化の妨げとなる「フリーライダー(裏切り者)」について、従来(こっそり利益をかすめとる騙し屋)とは違うタイプの裏切り者(力の誇示によって他者を制圧して利益を独り占めする暴君)の脅威を論じている点
- 利己的な暴君を排除できない理由として、ヒトの高い学習能力によって生じた遺伝子型と表現型の大きな乖離が考えられる点
- ヒトの利他性の進化を考えるうえで、内面的な認知と感情制御の能力を考慮している点
私はずっと以前から「ヒトはなぜ為政者にこんなに従順に従うのか?」という疑問を持っていました。リチャード・ドーキンスの『神は妄想である』のなかには、「先史時代には経験豊富な年長者や実力者の言うことに従ったほうが生存確率が高かったので、そのような形質が進化した」という趣旨のことが述べられており、「なるほど、そうだったのか!」と納得していましたが、それ以外の理由はないのだろうか?とも思っていました。たとえば、力の誇示による制圧など、別の理由もありそうです。
ただし、前にも書いたように、本書は相変わらず進化を群淘汰で説明していたり、最近の研究成果から見るとすでに古くなってしまった知見が含まれているらしいので、その点は注意して読もうと思います。
【追記】途中まで読み進めて、本書で論じたれているのはもっぱら、ゴリラ・チンパンジー・ボノボ・ヒトの共通先祖から始まって、約4万5千年前の狩猟採集民までの道徳や良心の進化の過程であって、約1万年前から現在に至るまで大きな変化にはほとんど触れられていないことが分かりました。私の関心は、最近の1万年になぜこんなにヒトが争うようになったのか?、なぜこんなに格差や差別が広がったのか?で、本書はそれにはあまり答えてくれないようです。
『人間の本性について』の著者のエドワード・O・ウィルソンは、この本に先立つ『社会生物学』によって長年にわたる社会生物学論争のきっかけを作った人です。彼に対する「それは遺伝子決定論だ」「社会的不公平を正当化している」といった批判の多くは、政治的イデオロギーや宗教的立場の違いも含めた誤解や曲解によるものだと思います。たしかに細部では、血縁淘汰を否定したり、群淘汰に固執したりと、理論的に正しくない面が多いのも事実ですが、自然科学と社会人文科学の垣根を越えた学際的な視点を持っている点は大いに評価できると思います。
私自身も「自由で機能する社会」のあり方を模索するにあたって、その前提として、そもそもヒトはどのような生物なのか、ヒトはどのような環境や生き方を好ましいと思うのかをきちんと押さえておく必要があると考えています。その意味で、ウィルソンの考え方を参考にしたいと思っています。
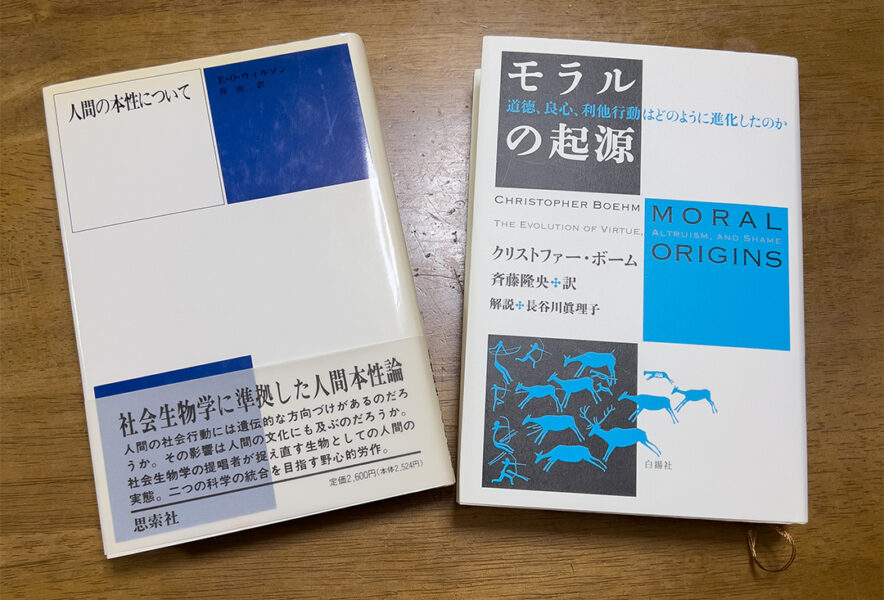
コメント